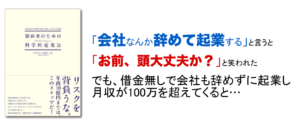
おはようございます
9月も最後の月曜日の朝です
9月も残すところあと2日
昨日は一日中所用対応
で、月曜日ということで
大河ドラマ「べらぼう」第37回
春町が自害し喜三二が去り政演も執筆を躊躇
歌麿は栃木の商人から肉筆画の依頼を受けた
松平定信は棄捐令、中洲の取り壊し
大奥への倹約など自らの改革を実行
その煽りを受けた吉原のために重三郎は政演
歌麿に新たな仕事を依頼するがていが反論した
ドラマのあらすじに関してはこちらへ
→大河ドラマべらぼう公式サイト
徳川家斉には53人の子供がいたことは
以前触れさせて頂きました
その中で一番に歴史に名前を残したのは
家斉にとっては次男となりますが後の
12代将軍徳川家慶ですが大河ドラマでは
1990年『翔ぶが如く』
1998年『徳川慶喜』
2008年『篤姫』
2021年『青天を衝け』
の4回も登場していました
ほとんど印象にはありませんでしたが(笑)
53人いた家斉の子ですが10歳以上まで
存命であったのは半数以下でほとんどは
幼少期に亡くなってしまっていたようです
そんな中で一番長く生きていたのは15男で
津山藩主松平斉孝の養子となった松平斉民で
77歳という長寿であったようです
津山松平家は徳川家康の次男結城秀康の五男
松平直基を祖とする藩で当初は10万石の家柄
しかし秀康の玄孫の代に継嗣ないまま藩主が夭逝し
5万石に減封されていましたがそれが将軍家斉の
15男斉民の養子入りで10万石に復したようです
流石に将軍の子が養子になる先が5万石では
体裁が悪いという事だったのかもしれません
松平斉民は1891年(明治24年)まで健在でしたが
明治24年というとロシアのニコライ皇太子が
刺された大津事件が起こった年でそんな時代に
徳川家斉の嫡男が生きていたとは不思議な気分です
斉民は1855年(安政2年)に養子の慶倫に
家督を譲りますがその3年後は江戸では
井伊直弼が大老に就任した年でした
津山市の出版した『津山城百聞録』によれば
アメリカからペリー艦隊がやってきた際に
多くの大名が「攘夷」を唱える中で斉民は
開国通商の必要性を説いた意見書を提出した
といった記録が残されているそうです
そうした考えの持ち主であっとから井伊直弼は
第11代将軍家斉の嫡男であった斉民の
幕閣入りを画策していたようですが
結局斉民は病気を理由に隠居した身である
ということで申し出を断ったとされているようです
子沢山であった家斉ではありましたが
家斉の男系男子の子孫は現在ではこの斉民の
流れだけになっているようです
次回、松平定信は学問や思想に厳しい目を向け
出版統制を行う、第38回「地本問屋仲間事之始」
という訳で
今日も一日頑張って行きましょう!



「【考察】大河ドラマ「べらぼう」第37回!」へのコメント
コメントはありません