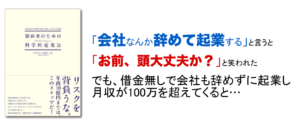
おはようございます
11月も2回目の月曜日の朝です
昨日は午前中はずっと事務所で作業
途中、電話対応数件
午後からは地元市役所で無料相談会の相談員
夕方事務所に戻り午前中の作業の続き
夜になり地元団体の集まりに参加
終了後事務所に戻り作業の続き
で、月曜日ということで
大河ドラマ「べらぼう」第43回
重三郎は歌麿が描く五十枚の女郎絵の
準備を進めていると歌麿が西村屋と組むと
耳にして、歌麿に会いに行くと…。
一方城中では松平定信は“大老”の座を
狙って動くが………
今回のドラマに関してはこちらへ
→大河ドラマべらぼう公式サイト
大老の地位を得ようと画策するも松平定信は
逆に失脚し老中の地位も失ってしまいました
定信が大老の地位をもくろんでいたというのは
個人的には初めて聞いた説でした
さて大老というと幕末の井伊直弼が
よく知られるところですが
大老は江戸幕府の職制の中で将軍の補佐役という役ですが
臨時に老中の上に置かれた最高職とされています
江戸時代の前には豊臣政権の頃に五大老と呼ばれる
職制がありましたがこちらはもう少し広義な意味
として大名家・執政機関の最高責任者群を指しました
大老という職制は徳川幕府創設時から設けられたものではなく
寛永15年(1638年)に3代将軍徳川家光が土井利勝・酒井忠勝を
老中から大老に格上げしたのが始まりとされるようです
その後、徳川家綱の時代には酒井忠清・井伊直澄が就任
また5代将軍徳川綱吉が堀田正俊にその職任命したことで
老中が幕府の最高職としての体裁が整ったとされています
このながれから大老職に就けるのは徳川譜代大名である
井伊家・酒井家・土井家・堀田家の
4家に限定されるという慣習ができあがったようです
劇中で例外として出てきた柳沢吉保は
厳密には大老ではなく大老格とされていて
厳密な意味では大老ではないかもしれないが
実質的には大老と同じ権限があったもの
江戸時代を通じて大老は全部で12人いましたが
そのうちの5人は井伊家、4人が酒井家からで
とくに後半はそのほとんどが井伊家からの任命でした
失脚した松平定信でしたがその後は
白河藩に戻り藩政の立て直しに尽力し
財政再建と産業振興
教育と福祉の充実
などで成果を上げ名君といわれる
働きをしたと言われています
次回、重三郎の前に駿府生まれの貞一と名乗る男が現れる
第44回「空飛ぶ源内」
という訳で
今日も一日頑張って行きましょう!



「【考察】大河ドラマ「べらぼう」第43回!」へのコメント
コメントはありません