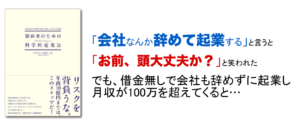
おはようございます
3連休の最終日の月曜日の朝です
昨日は朝からずっと事務所で作業
午前中には来客2件あり打合せなど
途中所用対応ののちに
午後からは来客3件あり打合せなど
あとはひたすら申請書類の作成
オンライン申請1件
で、月曜日ということで
大河ドラマ「べらぼう」第42回
身上半減から店を立て直した重三郎は妻ていから
懐妊を知らされ子どもの誕生を心待ちにする
一方城中では松平定信はその独裁的な振舞いから
幕閣内で孤立し始めていた
今回のドラマに関してはこちらへ
→大河ドラマべらぼう公式サイト
さて今回も歴史のマニアックな話題
人物の登場はありませんでしたが
触れなくてはならない人物の名前が登場
その名は大黒屋光太夫(だいこくやこうだゆう)
江戸時代に漂流からその葉をはせた人物といえば
誰もが思い浮かべるのはジョン万次郎ですが
実はこの時代にロシアに漂流し10年余りの
異国の地に暮らしたのがこの人物でした
大黒屋光太夫は江戸時代後期の
伊勢国奄芸郡白子(現在の三重県鈴鹿市)
の港を拠点とした回船の船頭でした
1783年1月、光太夫が船員15名とともに
乗り込んだ神昌丸は紀州藩の囲米を積み
伊勢から江戸を目指しましたが駿河沖で
暴風に遭い船は進路を外れて7か月間漂流
ロシアのアリューシャン列島の
アムチトカ島に漂着
光太夫たちは島の島民や滞在していたロシア人ら
とともに島での生活を余儀なくされまし
過酷な環境の中でロシア語を学び
互いに助け合いながら生き延びたましたが
4年後島に到来した難破船のロシア船の
船の再建を手伝ったことをきっかけに
ロシア本土への道を切り開くことに
その旅路で出会った
博物学者キリル・ラクスマンと出会いから
サンクトペテルブルクでエカチェリーナ2世への
謁見を果たし日本への帰還が許されました
1792年約10年におよぶ漂流の末
光太夫は北海道の根室で祖国の土を踏みました
異国の地で得た知識と航海術は
大黒屋光太夫をただの漂流者以上の
存在へと押し上げていましたが
江戸では幕府による聴取を受けるも
その見聞は『漂民御覧之記』や『北槎聞略』
として記録され蘭学の発展に寄与しました
老中松平定信は光太夫を利用して
ロシアとの交渉を目論んだようです
晩年の光太夫は比較的自由な生活を許され
江戸番町の薬園に居を構え故郷の伊勢とも
繋がりを保ちながら余生を過ごしたようです
光太夫らがロシア滞在中に得た情報は
日本の北方防衛の意識を高める契機となり
歴史の舞台裏で重要な役割を果たします
大黒屋光太夫を描いた作品と言えばこちら
→「おろしや国酔夢譚」
現在三重県鈴鹿市には
大黒屋光太夫記念館があるそうです
→鈴鹿市HPより
次回、重三郎は歌麿が西村屋と組むと耳にし…。
第43回「裏切りの恋歌」
という訳で
今日も一日頑張って行きましょう!


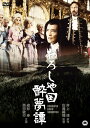
「【考察】大河ドラマ「べらぼう」第42回!」へのコメント
コメントはありません