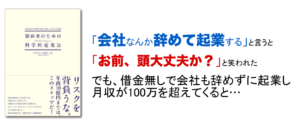
おはようございます
3月も終盤の月曜日の朝です
昨日は一日中事務所で作業
午前中に来客3件対応打合せ
午後には夕方に来客2件対応打打合せ
あとはひたすら申請書類作成と資料整理
で、今日は月曜日ということで
大河ドラマ「べらぼう」の第12回
昨年に続き吉原で行われる『俄(にわか)』祭り
その企画の覇権を巡り大文字屋と若木屋らの間で
戦いの火ぶたが切られたことを盛り上げようと
重三郎は30日間にわたる俄祭りの内情について
おもしろおかしく書いてほしいと平賀源内に依頼
すると執筆者として朋誠堂喜三二を勧められる
喜三二の正体と、実はあの男であった…………
吉原の俄(にわか)祭りは江戸時代に吉原で
行われていた即興芝居の一種であり「俄」とは
短期間に準備される即席の寸劇を指していました
吉原の俄の特徴として次の4点が言われています
①即興性と娯楽性
俄は台本に基づく正式な芝居とは異なり
その場の雰囲気に合わせたアドリブや
風刺を交えた演技が特徴とされています
吉原では遊女や芸者、商人たちが
日常の出来事や流行を題材にして
観客を楽しませるために演じました
②風刺とユーモア
当時の社会風刺や世相を巧みに取り入れた
演目が多く演じられていて権力者や町の有力者を
軽妙にからかう内容も人気を集めました
堅苦しい芝居とは異なり庶民に
親しまれる娯楽てして楽しまれました
③祭りとの結びつき
吉原では年中行事の一環として俄が行われ
特に夏祭りの時期には多くの俄が披露されました
商売繁盛を願い店同士で競い合うように
派手な演目か用意されていて多くの客を
楽しませることに力を入れていました
④芝居絵と出版文化への影響
祭りの盛り上がりを記録するために
俄の様子を描いた「芝居絵」や「絵草紙」が
出版されることもあったようです
これにより俄の文化は江戸市中にも広まり
庶民文化の一端を担うことになりました
吉原の俄はその後の落語や講談さらには
歌舞伎の演目にも影響を与えたとされていて
その即興性や風刺の精神は現代の大衆芸能にも
通じるものがあるといわれているそうです
次回、江戸城では意次が平蔵に
座頭金の実情を探るよう命じる…。
第13回「お江戸揺るがす座頭金」
という訳で
今日も一日頑張って行きましょう!



「【考察】大河ドラマ「べらぼう」第12回!」へのコメント
コメントはありません