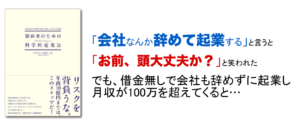
おはようございます
9月も2回目の月曜日の朝です
昨日は一日事務所で作業
ずっと申請書類の作成など
午後には来客1件対応打合せ
で、月曜日ということで
大河ドラマ「べらぼう」第34回
定信は老中首座に就くと厳しい統制を始める
処罰の危機となった南畝は絶筆を宣言する
そこで重三郎はある決意で意次の屋敷を訪れる
ドラマのあらすじに関してはこちらへ
→大河ドラマべらぼう公式サイト
田沼意次に代わって幕府の実権を握った松平定信
松平定信が行った改革「寛政の改革」といえば
歴史の教科書の中でも必須のアイテム
江戸時代の3大改革といえば
徳川吉宗の享保の改革
松平定信の寛政の寛政
水野忠邦の天保の改革
今回はその中でも寛政の改革(1787年〜1793年)とは
どのような改革であったのかその中身をみてみると
寛政の改革は田沼意次時代の重商主義に対して
重農緊縮政策へ転換という点がその特徴で
倹約令・棄捐令
囲米の制による備蓄
人足寄場の設置
旧里帰農令などの農村政策
寛政異学の禁に代表される思想統制
というのがその内容
これらの制作によって一時的に財政は安定しましたが
景気後退を招き、庶民の不満を買ったとされています
経済財政政策の面からみると
倹約令で大奥の費用削減や旗本・御家人に対する
贅沢を禁じることで浪費を抑え財政を安定化
棄捐令によって旗本・御家人の抱える借金を帳消しにし
旗本御家人を救済する一方で商人には困惑をもたらす
囲米の制により天明の飢饉への対策として
各藩に米を蓄えることを命じ米の備蓄を増やしました
七分積金により都市の経費の一部を積み立て、飢饉や
災害に備える基金とし幕府財政の安定化を図りました
農村政策としては
人足寄場の設置により都市に流れるホームレス状態の
無職者に対し石川島で職業訓練を施し社会復帰を支援
旧里帰農令により故郷へ戻る農民に旅費や補助金を支給し
農村人口の回復と農民の生活安定を図りました
社会思想政策としては
寛政異学の禁により幕府に都合の良い身分制度を
重視する朱子学を正学としそれ以外の学問を禁止
そして出版統制によって風紀の乱れを正し
好色本などの出版を制限しました
とこれらが改革が進められてゆきますが
特に最後の出版統制のよって重三郎は
大きな影響を受けることとなりそうですが
さてその辺はどのように描かれてゆくのでしょうか
定信の政を茶化した『文武二道万石通』によって
重三郎は逆に改革を勢いづかせてしまう
次回第35回「間違凧文武二道(まちがいだこぶんぶのふたみち)」
という訳で
今日も一日頑張って行きましょう!



「【考察】大河ドラマ「べらぼう」第34回!」へのコメント
コメントはありません