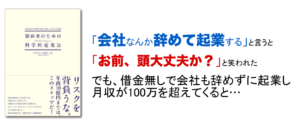
おはようございます
3月も最終日の月曜日の朝です
昨日は午前中に所用対応してから
事務所へ行き申請書類作成と資料整理
午後も引き続き事務所で引き篭もり作業
で、月曜日というけとで
大河ドラマ「べらぼう」第13回
重三郎は鱗形屋が再び偽板の罪で捕われた
との知らせを受けがそれは鱗形屋が各所に重ねた
借金の証文が金貸しの座頭に流れたことで
苦し紛れに罪を犯したということであった
その一方で江戸城内では旗本の娘が借金のかた
に売られていることが問題視されたことから
田沼意次は長谷川平蔵に金貸しの座頭を探らせる
ドラマのあらすじに関してはこちらへ
→べらぼう公式サイト
長谷川平蔵は言わずと知れた火付盗賊改方として
名を馳せた人物で池波正太郎作の「鬼平犯科帳」
のモデルとして小説やドラマにも描かれています
「火付盗賊」とは放火や大規模な盗みを働く
犯罪者を指しその取締役職である火付盗賊改方は
江戸の人々の治安を守る現在でいうところの
警視庁捜査一課にあたる重要な役割といえます
しかし平蔵は若い時期には遊郭に通いつめる等
いわば放蕩者であったということが史料にも
残されていると言われていますがしかしその後
多くの江戸庶民に頼りにされる存在となり
無宿人の更生施設である石川島人足寄場を創設する
など江戸庶民の治安維持のために功績を残しました
長谷川平蔵が火付盗賊改方となったのは1787年で
平蔵が42歳の時の抜擢でしたが当初は冬の間のみ
火付盗賊改方に就く「当分加役」という役でしたが
のちに通年における火付盗賊改方となったようです
親子2代で火付盗賊改方になったのは異例のことで
単に世襲でなく長谷川平蔵の能力が評価されていた
のは間違いなくて江戸時代の裁判記録である
「御仕置例類集」によれば長谷川平蔵が
火付盗賊改方として扱った事件の数多くが
記録として残されていて「神道徳次郎」「葵小僧」
といった当時世間を騒がせていた盗賊一味を
捕縛するという大きな功績を挙げていた
といわれています
次回、蔦重は大文字屋から空き店舗の話を聞き
独立し店を持てないかと考える
第14回「蔦重瀬川夫婦道中」
という訳で
今日も一日頑張って行きましょう!



「【考察】大河ドラマ「べらぼう」第13回!」へのコメント
コメントはありません