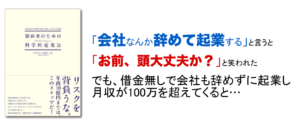
おはようございます
3連休の3日目の月曜日の朝です
昨日は一日中所用対応
で、月曜日ということで
大河ドラマ「べらぼう」第35回
老中松平定信の政を茶化して作った『文武二道万石通)』
はこれを目にした定信が勘違いをしたことで
逆に改革が勢いづいてしまい複雑な気持ちの
重三郎であったが定信が将軍補佐就任を知る
そんな中歌麿はかつて廃寺で
絵を拾い集めてくれたきよと再会
江戸城では家斉が大奥の女中との間に子をもうける…。
ドラマのあらすじに関してはこちらへ
→大河ドラマべらぼう公式サイト
11代将軍徳川家斉は城軍在位50年の長期政権で
子供の数が50人以上もいたことで知られています
劇中にも出てきた第一子が生まれたのは
1789年で長女として生まれた後の清湛院叔姫
母は側室のお万の方で家斉が満15歳の時の子
お万の方は幕府旗本平塚為義の娘で
当初は本丸御次でしたがのちに御中﨟となる
本丸御次とは仏間や茶道具、台所の整理整頓管理担当
更に最も重要な仕事は季節ごとのイベントの
プロデュースで遊芸の心得のある者が
選ばれたといわれているそうです
御中臈とは将軍付又は御台所付となりそれぞれの
身辺世話を担当となりますが将軍付の御中臈は
いわゆる器量の良い者が選ばれることが多く
将軍のお手がつくと側室となるパターンもしばしば
お万の方はまさのこのパターンで淑姫のあとに
男1人女2人の計四人を出産します
淑姫は後の尾張第10代藩主徳川斉朝の正室に
家斉の最後の子である第27女は1827年で
約38年後に出生した子でその間に17人の
正室側室間に計53人の子を儲けてます
それぞれの子がどのような生涯となったかも
気が向いたらそのうち触れたいと思います
次回
定信は重三郎の新作黄表紙に激怒し絶版を言い渡す
第36回「鸚鵡(おうむ)のけりは鴨(かも)」
という訳で
今日も一日頑張って行きましょう!



「【考察】大河ドラマ「べらぼう」第35回!」へのコメント
コメントはありません