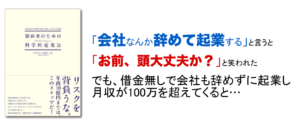
おはようございます
4月も3回目の月曜日の朝です
昨日は一日中ずっと事務所で作業
調べモノのと申請書類の作成など
で、月曜日というけとで
大河ドラマ「べらぼう」第16回
家基急逝の事件は確固たる証拠を得ぬまま幕引き
田沼意次は平賀源内に対しこれ以上の詮索
しないことを告げると源内は激怒して出ていく
重三郎は源内の住む“不吉の家”を訪ねると
奇妙な言動を繰り返す源内の様子が……..
ドラマのあらすじに関してはこちらへ
→大河ドラマべらぼう公式サイト
強烈なキャラで存在感を示していた
平賀源内も今回で登場は最後のようです
1728年高松藩志度浦(現材の香川県さぬき市)で
源内は藩の米を管理する「蔵番(くらばん)」を
務める父のもとに生まれました
「江戸の天才発明家」として名を馳せる才覚は
幼少期からすでに発揮されていたようで
源内少年は様々なからくりをこしらえては
家人や村人たちを感心させたといわれています
13歳頃から藩医のもとで本草学や儒学を学び
源内が数え年で22歳のときに父が亡くなると
家督を継いで父と同じく蔵番に就くものの
やがてその博識ぶりが評価されて藩主松平頼恭に
御薬坊主として仕えることになります
しかし才能あふれる源内は江戸遊学を許されます
江戸での源内は本草学者を訪ねてさまざまな
薬用の植物・動物・鉱物の研究をする傍ら
儒学も学びさらに国学者のもとで動植物の
名前を研究するなど知的好奇心を思う存分に
満たしたといわれています
その後自由な研修活動に没頭するため藩に脱藩を
申し入れ「他藩への仕官は禁止」という
条件付きでしたが希望は認めれました
自由になった源内は「東都薬品会」を開催し
これは日本初の博覧会ともされています
翌年には女形の荻野八重桐の溺死事件を
題材にして当時の世相を風刺した
『根南志具佐(ねなしぐさ)』を発表
実在の辻講釈師である深井志道軒をモデルにして
架空の諸国漫遊記で世相を風刺した
『風流志道軒傳(ふうりゅうしどうけんでん)』
を世に送り出しベストセラーとなり
「江戸戯作の開祖」とも言われました
現在のコピーライティングの先駆けとも言える
「土用の丑の日にうなぎを食べよう」という
キャッチコピーも源内の作といわれていて
これは夏に売れないうなぎ屋の相談に乗って
商売繁盛を助けたというエピソード
発明家であり、蘭学者であり、小説家でも
あった彼の人生は常識にとらわれない
アイデアと行動に満ちていて
日本のレオナルド・ダ・ヴィンチとも
表されるような存在だったそうです
ただその最後は劇中でも描かれたように
あまり華々しいものではなかったようです
次回、物語は次の舞台へ
第17回「乱れ咲往来の桜」
尚次回は本放送はお休みで第17回は再来週の予定
という訳で
今日も一日頑張って行きましょう!



「【考察】大河ドラマ「べらぼう」第16回!」へのコメント
コメントはありません