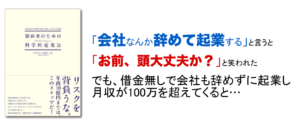
おはようございます
7月最初の月曜日の朝です
今日は七夕です
昨日は一日中事務所で作業
申請書類作成と資料整理
オンライン申請で2件申請
で、月曜日というけとで
大河ドラマ「べらぼう」第26回
冷夏による米の不作で米の値が昨年の倍
さらに奉公人も増え戯作者たちが集まる耕書堂は
米の減りが早いため重三郎も苦労する中、実母つよが
店に転がり込み髪結いの仕事で店に居座ろうとする
江戸城では意次が高騰する米の値に対策を講じるが
一向に下がらず業を煮やした紀州徳川家治貞が
幕府に対して忠告する事態に発展していた
ドラマのあらすじに関してはこちらへ
→大河ドラマ「べらぼう」公式サイト
今回から突然登場した重三郎の母「つよ」ですが
またとても面白いキャラクター設定のようです
蔦屋重三郎の生い立ちについて記された史料に
「喜多川柯理墓碣銘」というものがあるそうです
この作者は重三郎と同時代人の石川雅望で
狂歌に関心を寄せ大田南畝のもとで学び
「天明狂歌四天王の1人」とまで評された人物
この書によると重三郎が生まれたのは
「寛延三年庚午正月初七日」(1750年1月7日)のこと
「江戸吉原の里」で生まれましたが
重三郎の父は丸山重助という名で
また母は「津与」という名で
母は江戸生まれだったようです
両親の馴れ初めまではそこには
記されてはいなかったようですが
両親は重三郎が7歳の頃離婚し
津与は幼い重三郎を残して家を出ました
津与が病で亡くなったのちに
重三郎の依頼で大田南畝が記した
「実母顕彰の碑文」という墓碣銘に
「後移居油街、乃迎父母奉養」
(後、居を油街へ移す、乃ち父母を迎えて奉養す)
と記したそうで重三郎は大人になってから
両親を日本橋通油町の新居に迎えていた
ものと思われますのです
このあと母つよも演ずる女優さんの存在感から
それなりに重要な役どころのキャラクターとして
描かれるのかもしれません
次回、意知が誰袖を身請けする話がなくなる一方
道廣が治済に蝦夷地の上知の中止を進言する
第27回「願わくば花の下にて春死なん」
という訳で今日も一日
がんばって行きましょう!



「【考察】大河ドラマ「べらぼう」第26回!」へのコメント
コメントはありません