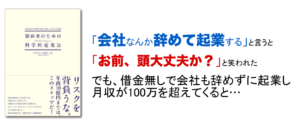
おはようございます
2月も最初の月曜日の朝です
昨日は午前中は事務所で作業
で、来客1件対応打合せ
午後には引き続き申請書類作成など
夕方から地元で開催の某イベントのお手伝い
で、月曜日ということで
大河ドラマ「べらぼう」の第5回
株仲間に入れなかったことで落胆する重三郎
そんなある日、唐丸の前にある男が現れた
唐丸の過去を知る男は唐丸を脅し次第に追い詰める
思い悩んだ末、脅された唐丸はある行動に出る
ドラマのあらすじに関してはこちらへ
→べらぼう公式サイト
株仲間を奨励して税を徴収した田沼の政治の田沼意次
株仲間を解散した天保の改革の水野忠邦
といった感じで中学校の社会の教科書で習いましたが
重三郎が入れなかったことで悔しい思いをした
株仲間とは江戸時代に商工業者が幕府や藩から許可を得て
結成したいわゆる同業組合のことをいいます
株仲間が作られていたのは商工業者が既得権を守るため
商品の生産販売を独占し商品の価格が下がりすぎないように
したり新興業者を排除したりすることが主な目的
江戸時代初期から山林や漁場を利用する権利や
米を仲買したり両替をする権利をはじめとした
営業上の特権が売買や譲渡の対象になっていて
これを「株」とよんでいました
そんな中で商工業者たちが同業者どうしで
協力して組合を作り株を失わないようにするため
結成されたのが株仲間というしくみでした
株仲間は当初は同業の問屋による私的な集団で
江戸幕府は当初は楽市楽座路線を継承した政策を
方針としいて株仲間のような組織が流通機構を
支配して幕府に対する脅威になる事を恐れて
禁令が出されるなど規制の対象としていましたが
享保の改革において商業の統制を図るためには
商工業者が組織化された方が望ましいとして
公認が与えられ代わりに上納金を納めることで
販売権の独占などの特権を認められるようになり
さらに田沼意次時代になると積極的に公認され
幕府の現金収入増と商人統制を張るようになります
その後天保の改革で一度解散となる株仲間は
のちに阿部正弘の指示により遠山景元によって
復活することとなりますが
明治維新後の1872年(明治5年)再び解散を命じられ
以降復活することはありませんでしたが
その後、商業組合といった形に改組されていったようです
現在株仲間の仕組みが残っていると
言われるのが日本相撲協会の年寄名跡で
一般に「年寄株」とも呼ばれていますが
その原型は江戸時代に形成された株仲間で
令和の世に至り数々の問題を抱えつつもなお年寄制度は
税制上の優遇措置を受けることができる公益財団法人の
なかにあっても元力士が引退後も協会に残りかつ
運営に携わるための条件としてには今も存続しています
次回、
重三郎は鱗形屋と新たな青本を作る計画を始めるが…。
第5回「鱗(うろこ)剥がれた『節用集』」
という訳で
今日も一日頑張っていきましょう!



「【考察】大河ドラマ「べらぼう」第5回!」へのコメント
コメントはありません