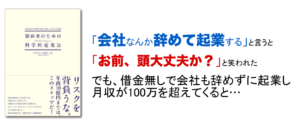
おはようございます
5月も2回目の月曜日の朝です
昨日は一日中ずっと事務所で作業
午前中に2件午後に1件来客あり打合せ
その他にオンライン申請1件
その他は申請書類作成など
で、月曜日というけとで
大河ドラマ「べらぼう」第18回
新たな青本の作者を探していた重三郎であったが
ある絵師が描いた数枚の絵を見比べるうちに
ある思いが巡り絵師を訪ねると捨吉と名乗る男がいた
さらに朋誠堂う喜三二に新作の青本の執筆を依頼する
重三郎であったが喜三二の筆が止まってしまった
との知らせを受ける……
ドラマのあらすじに関してはこちらへ
→大河ドラマ「べらぼう」公式サイト
以下ネタバレご注意願います(^^)
今期のストーリーの中心の一人は歌麿
喜多川歌麿は江戸時代の浮世絵師
美人大首絵で人気絵師になりました
歌麿作品は江戸時代の風俗や世相を写し出したもので
芸術的価値は海外でも高く評価されています
狩野派の絵師に師事して絵の修行を始めた歌麿は
当時流行していた黄表紙、洒落本、狂歌本などの
本の挿絵が絵師としてのスタートと言われています
黄表紙とは絵入りの小説で男女の色恋沙汰がテーマでした
洒落本とは遊郭の人間模様を主題とした本で
客と遊女の会話なども紹介されていたようです
狂歌本とはいわゆる詩画集で狂歌とは短歌の一種で
しゃれや世相を風刺する内容の歌でした
劇中では出生から過酷な人生を歩んでいた歌麿は
実際のところは生年・出生地・出身地などは不明
ただ生年に関しては没年からの逆算で1753年と
されることが多いようです
出身に関しては、川越説と江戸市中説の
2説が現在では有力をされているようですが
他にも京・大坂・近江国・下野国などの説も
歌麿は幼名は市太郎でのちに勇助
初めの号は豊章としていましたが天明初年頃から
歌麻呂・哥麿と号するようになったようです
次回、
鱗形屋のお抱え作家恋川春町は鶴屋で書くことが決まる
第19回「鱗(うろこ)の置き土産」
という訳で
今日も一日頑張って行きましょう!



「【考察】大河ドラマ「べらぼう」第18回!」へのコメント
コメントはありません