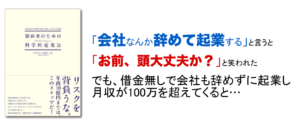
おはようございます
5月も最後の月曜日の朝です
昨日は某団体の行事で遠方へ
夜になり事務所に戻り資料確認など
で、月曜日ということで
大河ドラマ「べらぼう」第21回
『菊寿草』で『見徳一炊夢』や耕書堂が高く
評価され重三郎は須原屋と大田南畝の家を訪ねた
そこで近頃江戸で人気が出ている“狂歌”を知り
南畝から「狂歌の会」への誘いを受ける
一方江戸城では田沼意次は家治が次期将軍に
一橋家の豊千代を御台所には種姫を迎える意向で
あることを治済に伝え将軍後継問題は
決着するかに思われたが………
ドラマのあらすじに関してはこちらへ
→大河ドラマべらぼう公式サイト
以下ネタバレご注意願います(^^)
今回のストーリーの中心の一人は大田南畝
大田南畝は天明期を代表する狂歌師であり御家人
勘定所勤務として支配勘定にまで上り詰めた
幕府官僚であった一方で文筆方面でも
高い名声を持ったとされています
膨大な量の随筆を残す傍らで狂歌、洒落本、漢詩文、
狂詩などの作品も多く輩出したと言われていて
その中でも特に狂歌では高く評価され
唐衣橘洲・朱楽菅江と共に狂歌三大家と言われています
南畝を中心にした狂歌師グループは
山手連と称されました
狂歌とは、5・7・5・7・7の定型にのせて
日常の出来事を詠じたり社会風刺を行ったり
する和歌のことをいいます
遊び心を重視し古典のもじりや洒落を効かせる
のが特徴で季語は必要とせず
あえて俗語を用いて詠むのが慣例
このような狂歌が流行った背景には田沼意次による
自由化政策が大きな役割をはたしていたと
言えるのかもしれません
江戸城では次期将軍継嗣に一橋家の豊千代が
家治の養子となり次の時代への準備が着々と
進められて行っていました
豊千代は後の11代将軍家斉となりますが
家斉は約50年間という徳川幕府最長の期間
将軍に在位していたことと53人もの子供が
いたという人物でしたが家斉がどのような
キャラクターとして描かれ誰がどのように
演じるのかとても興味深いです
次回、
田沼意次は蝦夷地の上知の件で動き出す
第22回「蝦夷桜上野屁音(えぞのさくらうえののへおと)」
という訳で
今日も一日頑張って行きましょう



「【考察】大河ドラマ「べらぼう」第21回!」へのコメント
コメントはありません